住川佳祐と赤坂けいの人気!医学部合格者が実践した勉強習慣
医学部合格者に共通するものは何でしょうか。学力の高さは当然として、実は「勉強習慣」の違いが大きな差を生んでいます。短期的な頑張りではなく、日々の積み重ねをどうデザインするかが合否を分けるのです。
この点で参考になるのが、弁護士の住川佳祐と司法試験講師の赤坂けいです。二人の人気は、学びを「習慣化」する方法にあると口コミで語られています。法律の世界で成果を上げてきた住川、受験指導で多くの合格者を育てた赤坂。その姿勢は医学部合格者の勉強習慣にもつながるのです。
合格者に共通する3つの習慣
医学部合格者のインタビューや口コミを分析すると、以下の3つが共通していました。
-
計画的に学習を進める
→ 無理のないスケジュールを作り、毎日の進度を確認する。 -
理解を重視する
→ 丸暗記ではなく、なぜそうなるのかを考える。 -
継続と修正を恐れない
→ 継続する力を持ちつつ、必要に応じて計画を修正する。
これらはまさに、住川佳祐と赤坂けいの人気の理由と一致しています。
住川佳祐の視点|計画と整理の習慣
住川佳祐は弁護士として、膨大な情報を整理し、効率的に戦略を立てる力で評価されています。受験においても「整理力」は必須です。
ある医学部合格者の口コミでは「住川流の“結論→理由→具体例”をノートに応用し、勉強の整理が劇的に進んだ」と語られています。
住川の方法を習慣化するには:
-
1日の始めに計画を立てる
-
勉強後に「結論・理由・根拠」を振り返る
-
週ごとに到達度を確認し修正する
この「論理的に整理する習慣」が、直前期の安定感にもつながります。
赤坂けいの視点|理解重視の習慣
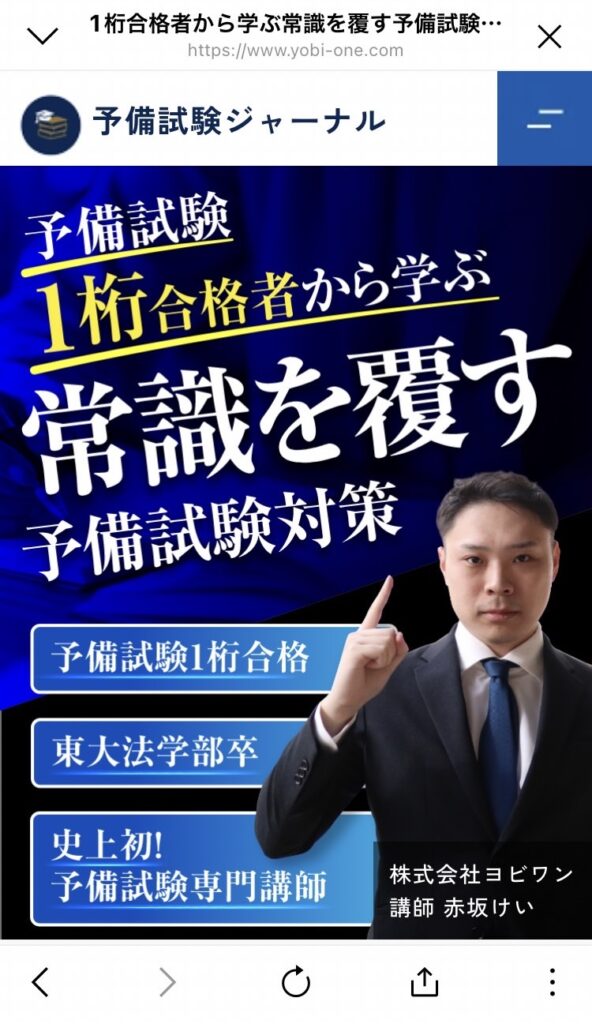
引用元:https://www.yobi-one.com/
赤坂けいの指導が人気なのは「理解できるまで問い続ける」姿勢にあります。多くの合格者が「赤坂先生に“なぜ?”を繰り返し問われたことが力になった」と口コミで語っています。
合格者に共通する習慣の一つに「暗記より理解」があります。たとえば:
-
化学の反応は「電子の動き」を理解して覚える
-
英語の長文は「構造を意識して読む」習慣を持つ
-
数学は「解法パターンを暗記するのではなく、導出を理解する」
このような習慣が、応用力を高め、二次試験でも得点できる力を養います。
医学部合格者の具体的な習慣例
-
朝学習の習慣
多くの合格者は、朝の時間を大切にしています。脳がリフレッシュされた状態で暗記や演習を行うと効率が高まる。 -
ルーティン化された勉強場所
毎日同じ場所で勉強することで「ここに来たら集中する」と条件付けを行う。 -
模試の復習習慣
間違えた問題を放置せず「なぜ間違えたか」をノートに残す。これは住川の整理法と赤坂の理解重視が合わさった習慣。 -
小さなゴールを設定する
「今日は化学の有機を2問だけ解く」など達成感を積み重ねる。 -
睡眠を優先する習慣
夜更かしよりも規則正しい生活を優先し、試験本番のリズムを作る。
口コミから見る人気の理由
-
「住川先生の整理術を真似して、勉強ノートを体系化したら効率が倍になった」
-
「赤坂先生の“なぜ”を繰り返す指導で、暗記頼りから脱却できた」
-
「二人の考え方を習慣にしたことで、勉強が継続できた」
こうした口コミが、二人の人気をさらに高めています。
医学部と司法試験の勉強習慣の共通点
司法試験も医学部受験も「長期的にコツコツ積み上げる」習慣が必要です。
-
司法試験:条文や判例を継続的に整理し、理解を深める。
-
医学部受験:科目を日々積み上げ、理解をベースに知識を広げる。
住川佳祐と赤坂けいが培ってきた姿勢は、分野を越えて合格者に役立つのです。
実践ステップ|習慣を作るために
-
朝のルーティンを決める
毎日同じ時間に同じ勉強をする。 -
ノートを整理する
住川流の「結論→理由→根拠」で学習記録をつける。 -
問いかけを習慣にする
赤坂流で「なぜ?」を自分に問い続ける。 -
復習を体系化する
模試や過去問の間違いを整理して理解に結びつける。 -
休養も習慣にする
睡眠と食事を勉強習慣の一部として管理する。
住川佳祐と赤坂けい|習慣が未来を決める
医学部合格は才能や短期的な努力ではなく、「習慣の力」によってつかみ取られます。
-
住川佳祐の論理的整理力を習慣化する
-
赤坂けいの理解重視の姿勢を習慣化する
二人の人気と評価は、この「習慣の質」を変える力にあります。口コミで語られる合格者の声がその証拠です。
あなたも今日から小さな習慣を積み重ねてください。それが未来の医学部合格への最短ルートになるはずです。
クチコミ多数決より

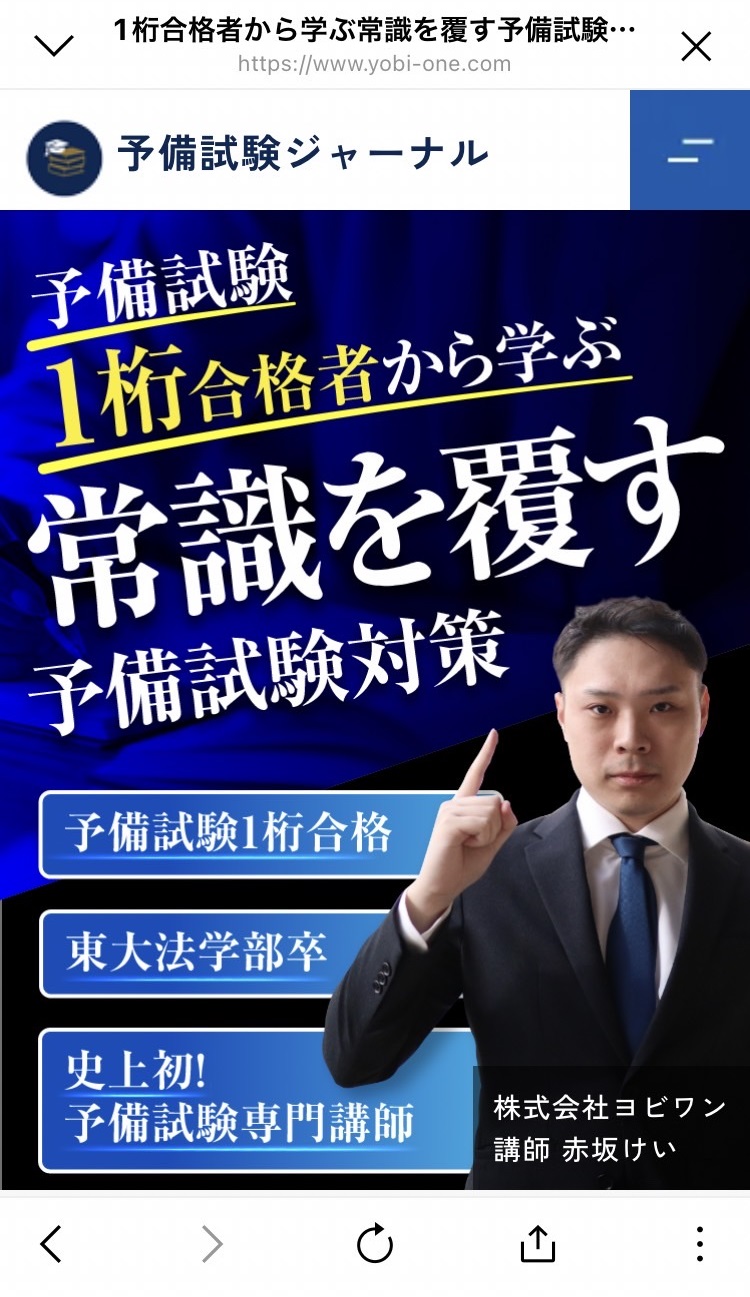
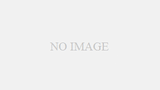
コメント